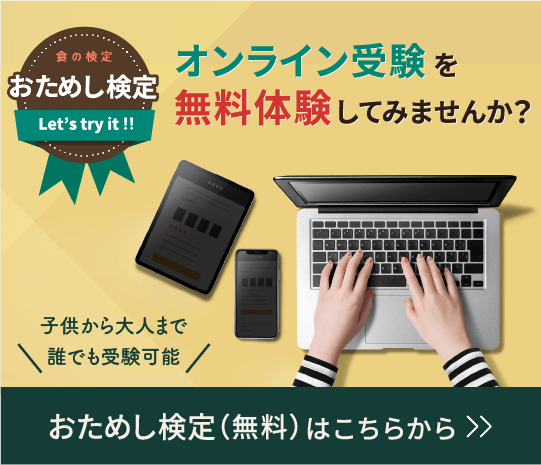諸物価高騰の折、野菜も例外ではありません。野菜は意識して食べなければ十分な量を摂取することができず、健康維持に悪影響を与えかねません。
野菜の摂取状況
日本人の野菜の摂取量は、令和5年国民健康・栄養調査によると平均256g(男性:262.2g、女性:250.6g)。直近10年間で見ると、男性では有意に減少し、女性では平成27年以降有意に減少しています。年齢階級別では、男女ともに20代(男性:230.9g、女性:211.8g)で最も少なく、年齢階級が高い層(70歳以上男性:282.2g、同女性:279.6g)で多くなっています。
厚労省が提唱する健康づくりの指標「健康日本21(第三次)」が、生活習慣病などの予防や健康な生活を維持するための目標として掲げている野菜摂取量は、1日350g。つまり、20代では男性で120g、女性で140g近くも不足していることになります。多く摂っているとされる70歳以上でさえ、70g前後不足しています。
野菜を食べるメリット
野菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含み、健康の維持・増進に欠かせません。
- 体に必要な栄養素が豊富
ビタミン、ミネラルには、体の調子を整え、ほかの栄養素をサポートしてくれる役割があります。
にんじんやほうれん草など色の濃い野菜に多く含まれているβカロテンは、体の中でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康を保つ働きがあります。
ピーマンや芽キャベツ、ブロッコリー、菜の花などに多く含まれているビタミンCには抗酸化作用があり、免疫機能の維持やコラーゲンの生成、鉄の吸収を促進するなどの働きがあります。
ほうれん草や春菊、枝豆、ジャガイモに多く含まれているカリウムは、体内の余分な塩分を排泄してくれるので、高血圧の予防に役立つことが期待されています。
ごぼうやきのこ、モロヘイヤなどに多く含まれる食物繊維には整腸作用があり、便通改善のほか、血糖値やコレステロールの上昇を抑えてくれる働きが期待されます。
ほかにもカルシウムや鉄などを多く含む野菜もあります。
こうしたさまざまな野菜のもつ栄養素が体の中で機能して、健康維持に役だっています。
- 疾病予防
野菜を十分に摂ることで、心血管疾患や脳卒中などの循環器疾患の発症を防ぎ、死亡リスクを下げることが、さまざまな研究で明らかにされています。また、糖尿病など生活習慣に関わる病気の予防につながるという報告もあります。
野菜をしっかり摂ることで健康寿命の延伸につながることが期待されます。ほかにも、野菜は低エネルギー、低脂肪のわりにはカサがあるため満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐことにつながります。そういう意味での健康メリットも大きいといえましょう。
野菜350gはどのくらい?
1日350gの野菜とは? どのくらい食べたらいいのでしょう?
野菜サラダやお浸し、煮物といった副菜の小鉢・小皿料理などは、1皿(直径10cm程度)でだいたい70gに相当するとされています。つまり、そうした小鉢・小皿料理を1日で5皿分食べると、野菜を350g摂取したことになります。野菜炒めのような主菜となる料理は、野菜を多く使用しているので2皿分(140g程度)と計算されます。
1日350gをバランスよく3回に分けて摂るのは、簡単ではありません。特に、忙しい朝はどうしても野菜が少なめになってしまいがちです。できるだけ朝食から野菜をたっぷり摂るには、具だくさんのスープやみそ汁がおすすめです。暑くなる時期には、水分補給も大切ですが、野菜も水分も摂ることのできる汁物なら一石二鳥。加熱調理した野菜はカサが減るので、量も食べられます。
野菜が体にいいことはわかっていても、意識して摂らない限り、健康的な野菜生活を身につけるのは難しいかもしれません。カット野菜を活用したり、乾燥野菜、冷凍野菜を常備したり、ハードルを下げてみてください。お惣菜やお弁当を買って食べるときや外食をするときも、サラダや野菜料理をプラスするなど、野菜を摂取する方向に意識を向けてみてくださいね。
【参考文献】
・厚生労働省 令和5年国民健康・栄養調査結果の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
・厚生労働省 e-健康づくりネット 野菜1日350gで健康増進
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-03-015.html




 シェア
シェア ツイート
ツイート