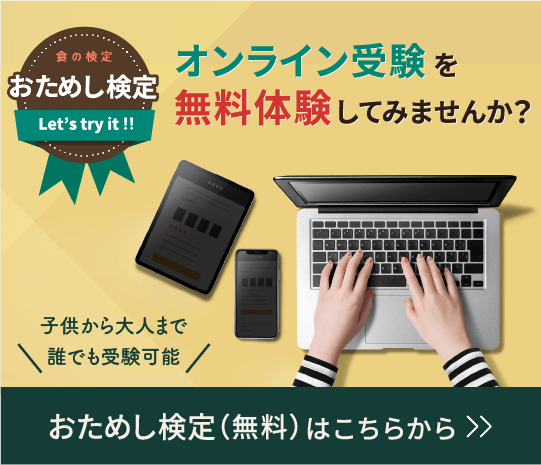ジメジメとうっとうしい梅雨の時期に気をつけたいのが「食中毒」です。今回は食中毒を防ぐにはどうしたらいいかをお伝えします。
食中毒とは
食中毒とは、食中毒を起こすもととなる細菌やウイルス、有害な物質がついた食べ物を食べることによって、腹痛や下痢、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことです。食中毒の原因によって症状や発症するまでの時間はさまざまですが、場合によっては命に関わることもあります。
ノロウイルスなどのウイルスによる食中毒は冬に多くなりますが、腸管出血性大腸菌やカンピロバクター、サルモネラ菌などの細菌による食中毒は気温が高く、湿気が多い6〜9月ごろに増えやすくなります
食中毒予防の原則
細菌性とウイルス性食中毒には、それぞれ下記のような予防の原則があります。
○細菌性食中毒
細菌性食中毒の予防の原則は3つ。
・細菌を食べ物に「つけない」
・食べ物に付着した細菌を「増やさない」
・食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」
それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
- 細菌を食べ物に「つけない」
食べ物に細菌をつけないことが大前提です。そのためには、調理の前はもちろんのこと、保存時、食事の前にも手洗いを徹底しましょう。石けんを使って、指と指の間、爪の間、手首までまんべんなく洗うこと。
野菜や果物、魚など食材の表面に細菌がついている可能性があるので、食材は調理する前にしっかり洗うこと。食材を保存する場合も、肉や魚の汁がほかの食材につかないようにそれぞれ袋に入れるなどといった配慮が必要です。
冷蔵庫内を清潔にしておくことや詰め込み過ぎないこと、包丁・まな板・ボウルなどの調理器具はきれいに洗って使うことも心がけてください。
- 食べ物に付着した細菌を「増やさない」
細菌は時間とともに繁殖し、環境次第で急激に増加します。そのため食べ物の保存方法には気をつける必要があります。生ものや調理した食べ物は暖かいところに置いておくと細菌が増殖しやすくなります。購入した食材は、すぐに冷蔵庫に入れるなど適切に保存し、出来上がった料理はなるべく早めに食べきること。
最近はテイクアウトを利用する方も多いと思いますが、こちらも早めに食べるようにし、食べきれなかった分は常温に長く放置しないこと。
冷蔵庫(10度以下)・冷凍庫(-15度以下)の適正温度もチェックしておきましょう。
- 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」
細菌をやっつけるには、「加熱」することです。生ものや加熱が不十分なものは細菌が繁殖しやすく、食中毒の危険性が高まるため、食材をしっかり加熱調理することが鍵となります。細菌の多くは75℃で1分以上加熱すると死滅するので、じっくりと食材の中心部まで火を通すようにします。
また、肉や魚を扱った調理器具は細菌がついている可能性があるため、熱湯をかけたり台所用殺菌剤を使ったりするといいでしょう。
○ウイルス性食中毒
ウイルス性食中毒の予防の原則は4つ。
・ウイルスを調理場内に「持ち込まない」
・食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」
・食べ物にウイルスを「つけない」
・付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」
ウイルスを調理場に持ち込まないためには、まず、調理者自身がウイルスに感染しないこと、調理器具や調理環境など調理場全体がウイルスに汚染されないようにすることが大切です。そのためにも調理者の健康管理が重要であり、体調不良のときには調理をしないことも考えるべきでしょう。
細菌やウイルスは目に見えないため、食中毒を完全に防ぐのは難しいと思われがちですが、上に挙げた予防原則を肝に銘じ、日ごろの食材の管理や調理方法、体調管理によって予防することができます。運動、栄養、休養のバランスを整えて、規則正しい生活を送り、健康維持に努めることで、食中毒にかかりにくい体づくりを心がけましょう。
【参考文献】
・農林水産省「子どもの食育」
・厚生労働省「家庭での食中毒予防」
ライター:山下 真澄
管理栄養士|日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士|
食育インストラクター|一級惣菜管理士|調理師




 シェア
シェア ツイート
ツイート