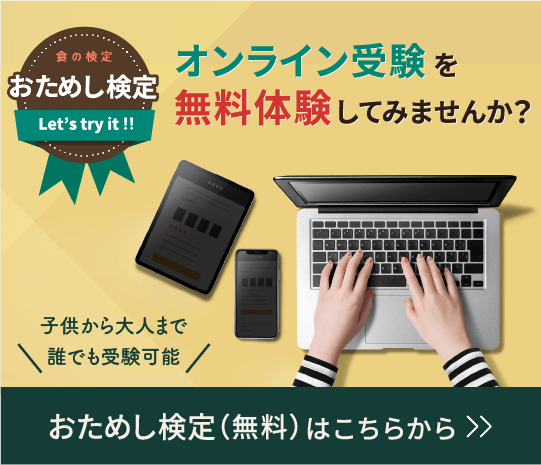健康診断で「脂肪肝」という結果に驚き、不安になったことはありませんか? 今回は、「脂肪肝」とは何か、その予防・改善方法などについてもお伝えします。
肝臓の働き
まずは、肝臓の主な働きからおさらいしましょう。
肝臓は胃や腸で消化・吸収された栄養をエネルギーとして蓄え、体に必要な成分に変える「代謝」、体内の有害な物質を無害化する「解毒作用」、脂肪の吸収をしやすくする消化液の一種である胆汁を作り分泌する「胆汁の合成・分泌」などの役割があります。
肝臓には痛みを感じる神経がないため、ある程度病気が進行しないと自覚症状がないので「沈黙の臓器」といわれています。
脂肪肝とは?
脂肪肝とは、肝臓に過剰な脂肪(中性脂肪)が蓄積された状態のことで、「脂肪性肝障害」とも呼ばれます。脂肪肝の状態が続くと、肝炎や肝硬変などを起こし、状況によっては肝臓がんへと進行していく可能性もあるので、放置しておくのは禁物です。
摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、余分なエネルギーは脂肪として体に蓄積されます。その脂肪は肝臓にも蓄積され、「脂肪肝の超音波診断基準」によれば、肝細胞の5%以上に脂肪化が認められる肝臓を「脂肪肝」と定義しています。
脂肪肝の原因は、過剰なアルコール摂取や不規則な生活習慣、食べ過ぎ、栄養バランスの崩れ、肥満などで、一部、遺伝的な原因もあります。
アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝
脂肪肝には、アルコールの飲み過ぎによる「アルコール性脂肪肝」とアルコールとは関係なく、過食などによる「非アルコール性脂肪肝」があります。
アルコール性脂肪肝は、文字通りアルコールの過剰摂取によるもの。アルコールは肝臓で分解されますが、その際に中性脂肪の合成が行われます。分解する量が多くなると、中性脂肪の合成が高まるため、どんどん肝臓に中性脂肪が蓄えられてしまいます。この状態が続くとアルコール性肝炎や肝硬変、肝臓がんなどに進行する場合があります。
非アルコール性脂肪肝は、アルコールに由来しない脂肪肝で、肥満や脂質異常症、糖尿病、高血圧、ストレスなど生活習慣病と合併しやすいのが特徴です。最近、この非アルコール性脂肪肝の方が増えてきています。お酒を飲まないから、肝機能は大丈夫というわけではありません。
前述したとおり、肝臓は沈黙の臓器ですから、脂肪肝や炎症があっても初期段階では自覚症状がなく、健康診断のエコー検査などで発見されるケースがほとんどです。無症状だからと放置していると、知らないうちに進行して肝炎や肝硬変などを発症し、さらに動脈硬化や糖尿病などを引き起こすこともあります。
脂肪肝の予防・改善
脂肪肝の予防・改善には、なんといっても過度のアルコールを避けること、適度な運動、バランスのよい食事が大切です。
運動では、肝臓についた脂肪を燃焼させるため、脂肪燃焼効果が高い有酸素運動がお勧めです。ウォーキングやジョギング、踏み台昇降などを、自分のペースに合わせて無理なく継続して行うこと。
食事では、主食、主菜、副菜を毎食整えるように心がけ、欠食や過食は避けること。欠食は脂肪の吸収を高め、血糖コントロールを悪くしてしまうので、糖尿病リスクを高めることにつながります。過食も脂肪を蓄えやくするので肥満の原因になります。腹八分目にして適正体重を心がけ、体重オーバーにならないようこまめにチェックしましょう。
アルコール性脂肪肝の方には特に禁酒や節酒をお勧めします。休肝日を設けて肝臓を休めてあげたり、飲む量を決めて飲んだり、間にソフトドリンクなどを挟んだり、ダラダラと飲まない、ながら飲みはしないなど…。自分の飲み方を振り返り、飲みすぎにならない飲み方を考えてみてください。
【参考文献】
・厚生労働省 健康日本21アクション支援システム〜健康づくりサポートネット〜
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-033
・日本超音波医学会 脂肪肝の超音波診断基準
https://www.jsum.or.jp/uploads_files/guideline/shindankijun/fatty_liver.pdf




 シェア
シェア ツイート
ツイート