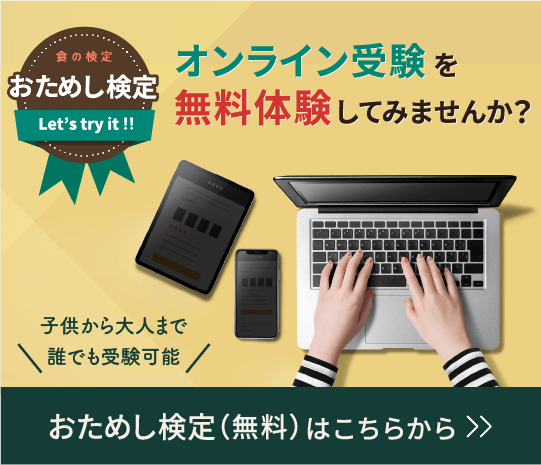若い女性の痩せすぎによる健康への影響が問題になっています。SNSや雑誌などで、痩せていることは美しいという価値観が根づき、「痩せたい!」とダイエットに励む人が多いのですが、極端に痩せてしまうと、体に与える悪影響が大きいことがわかっています。女性にとって「美」は永遠の憧れですが、「美」を追求するあまり、偏った食生活や無理なダイエットをすると…。今回は、痩せすぎによる健康問題についてお伝えします。
若い女性の「痩せ」の現状
令和5年「国民健康・栄養調査」によると、体格指数(BMI)が18.5未満の「痩せ・低体重」の者の割合は、女性全体で12.0%、20〜30代女性では20.2%です。ここ10年では大きな増減は見られませんが、痩せはさまざまな健康障害のリスクを高めるため、厚労省の「健康日本21」では、その割合を減少させることが目標となっています。特に先進国の中でも日本は、女性の痩せが高い割合となっているため深刻な状況です。
こうした現状を踏まえ、日本肥満学会は2025年4月、日本の若年女性の痩せすぎ傾向を新たな疾患概念として「FUS(Female Underweight/Undernutrition Syndrome:女性の低体重/低栄養症候群)」を提唱しました。
「痩せ」による健康と栄養問題
「肥満」は好ましからざること、病気になりやすい状態というイメージがけっこう浸透していると思いますが、「痩せ」はどうでしょう? 不健康というイメージを抱く方は少ないかもしれません。しかし、痩せの健康への影響は決して侮れません。痩せによる低体重や低栄養状態が続くことで、月経周期異常・骨密度の低下・骨粗鬆症・貧血・低血圧・筋力低下・髪質や肌質への影響・冷え性・不安や落ち込み・脂質異常症・糖尿病のリスクなどさまざまな健康障害を引き起こしてしまいます。
偏った食生活や極端な食事制限をする誤ったダイエットによって、筋力や体脂肪が減少してしまうと、ホルモンの分泌が乱れ、月経異常や無月経を起こしてしまいます。
また、食事を制限することで栄養素が偏り、骨の材料不足で骨密度の低下を招き、鉄分の材料不足で貧血になるなど、さまざま障害を招きます。
痩せたい願望が深刻化していくと、拒食症や過食症を招く恐れもあります。これは体重増加に対する強い恐怖感やその反動からくるもので、思春期から青年期早期にかけて発症すると考えられています。拒食症や過食症を一度発症してしまうと、辛いのはもちろんですが、完治するまでに長い時間を要します。
生まれてくる赤ちゃんにも影響が・・・
痩せは低栄養状態です。この状態で妊娠した場合、胎児に十分な栄養が行き届かず、2500g未満の低体重児の出産につながることがあります。低体重で生まれた赤ちゃんは、体内にエネルギーを溜め込みやすい体質になり、将来、糖尿病や高血圧といった生活習慣病になるリスクが高くなると考えられています。
大きな健康障害につながりかねない「痩せ」。自身の健康と将来生まれてくる子どもの健康のためにも、日ごろから、適切な栄養摂取を心がけていただきたいと思います。
【参考文献等】
・厚生労働省 令和5年「国民健康・栄養調査」の結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html
・厚生労働省 健康日本21アクション支援システム〜健康づくりサポートネット〜
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-02-006
・日本肥満学会「閉経前までの成人女性における低体重や低栄養による健康課題」
https://www.jasso.or.jp/data/Introduction/pdf/academic-information_statement_20250416.pdf




 シェア
シェア ツイート
ツイート