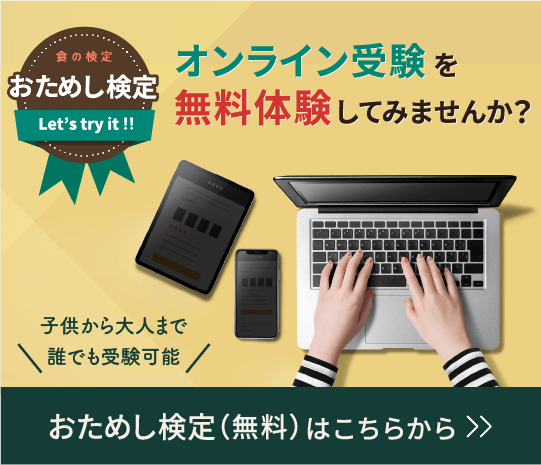前回に引き続き、「女性アスリートの三主徴」のうち、今回は「視床下部性無月経」と「骨粗鬆症」についてお伝えします。
視床下部の働き
女性アスリートの三主徴の発端は「利用可能エネルギー不足」です。運動によるエネルギー消費量に見合った食事からのエネルギー摂取量が確保されていない状態が続くと、体脂肪がエネルギーとして使われます。脂肪はホルモンなどの生理活性物質を分泌するのに必要ですが、体脂肪がエネルギーとして使われて極端に減ってしまうと、視床下部の働きが乱れてしまいます。
視床下部は体温調節や血圧、睡眠など生体のリズムを調節しています。また、女性ホルモンの分泌をコントロールする司令塔の役割があります。
視床下部の働きが乱れ、女性ホルモンの分泌が止まってしまうと、月経も止まってしまいます。これを視床下部性無月経といいます。
さらに、骨にまで悪い影響を及ぼしてしまいます。
脂肪細胞から分泌されるレプチンは、骨の形成にも関わっており、体脂肪が減少することで脂肪細胞も減少します。すると、骨が形成されず、骨折のリスクも高まってしまいます。
また、月経が止まると女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が低下します。すると骨の代謝が悪くなり、骨密度が低下し、疲労骨折や骨粗鬆症の原因となってしまいます。
視床下部性無月経
無月経とは、これまであった月経が3か月以上停止した状態のことをいいます。要因として、利用可能エネルギー不足はもちろん、それ以外に精神的、身体的ストレスや体重、体脂肪の減少、オーバートレーニングなどが挙げられます。これらの要因が続くと、無排卵、月経不順となり、無月経を招きます。ある日突然起こるわけではないため、無月経になる前に対処し予防することが大切です。
月経が来なくてラクと思っている選手も中にはいますが、月経が来ないことは実は、危機的な状況であり、一度無月経になると改善するのに時間がかかり、エストロゲンが低下してしまうため、疲労骨折の頻度も高くなります。
また、無月経状態は、発育やトレーニング効果に影響を及ぼします。つまり、パフォーマンス低下につながってしまいます。
骨粗鬆症
骨粗鬆症とは、「骨強度の低下により、骨折のリスクが高まることを特徴とする骨疾患」のこと。一般的には閉経後の女性や、高齢者に多いことが知られていますが、若い女性でも、エネルギー不足や栄養不足、無月経などで骨量が減少し、疲労骨折の危険性が高まります。
骨形成には、カルシウムはもちろん、ビタミンK・D、コラーゲンなどさまざまな栄養素が関わっています。無理なダイエットや食事量が少ないことによってエネルギー不足になると栄養不足を招き、その結果、骨量が減少し骨折のリスクが高まってしまいます。
エストロゲンは骨の成長にとって大切なホルモンです。したがって、正常に月経があることは、骨の成長に重要です。
骨量は、12歳ごろから急激に増え、20歳で最大となります。その大事な時期にエネルギーや栄養不足を招くと、将来の骨の状態に悪影響を及ぼしてしまいます。
競技のためにと体を酷使してしまうことも多々あると思いますが、実は知らない間に、体が悲鳴をあげていることも少なくありません。自身の体のことを知り、大切にしながら競技に臨んでほしいと思います。
しっかり食べて、しっかり睡眠! これが大切です。
【参考文献】
・日本スポーツ協会「女性アスリートの特性」
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/AT/ATtext2022_Vol.3_p169-174_20250430.pdf
・日本スポーツ振興センターハイパフォーマンススポーツセンター「成長期女性アスリート指導者のためのハンドブック 女性アスリートの三主徴」
https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/Portals/0/resources/jiss/column/woman/seichoki_handobook_5.pdf




 シェア
シェア ツイート
ツイート